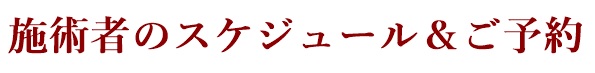こんにちは。院長の小澤です。
ここ1~2年、子ども整体のニーズがとても増えているなと
肌で感じます。
親御さんからよくお伺いする悩みは
【お子さんの背中が丸まっている気がする】
【ぐにゃっとした姿勢でご飯を食べるのが気になる】
というものです。
実は、この子どもの姿勢の悪さには
「固有受容感覚の鈍さ」が深く関わっている可能性があります。
デジタル機器の普及や運動不足により、
子どもたちが、この「固有受容感覚」という
重要な感覚を十分に発達させることができず、
姿勢を上手に保てないことが多いです。
耳慣れない言葉「固有受容感覚」ですが、
日頃の生活で、誰もがいつも使っている感覚です。
今回はこの「固有受容感覚」についてから始まり、
背中の丸みや姿勢改善につながるご自宅でできるエクササイズまで、
分かりやすくご説明します。
固有受容感覚とは?子どもの発達における重要な役割
固有受容感覚とは、自分の体の位置や動き、力の入り具合を感じ取る
「体の内側からの感覚」のことです。
この感覚により、目を閉じていても手足の位置がわかり、
階段を見なくても安全に昇降でき、
適切な力加減で物を扱うことができます。
固有受容感覚は、筋肉や関節、腱にある特殊なセンサー(受容器)から
脳に送られる情報によって成り立っています。
子どもの成長過程において、
この感覚は姿勢の維持、運動能力の発達、集中力の向上など、
様々な面で重要な役割を果たしています。
特に、正しい姿勢を保つためには、
常に体の位置を感知し、必要に応じて筋肉の働きを調整する
固有受容感覚が不可欠になります。
固有受容感覚が鈍い人・こどものエピソード
必ずしも、すべての理由が固有受容感覚の鈍さから
来ているものではありませんが、
以下のような動作や行動は、
固有受容感覚が鈍い大人や子どものエピソードで
よく聞かれるものです。
・物や生き物をそっと握る、触ることが難しい
・物を投げ入れたり、壊したりと物の扱いが雑
・ドシンドシンと歩く、ドアを激しく閉める
・グミ、ガム、飴などの食感のものをよく噛みたがる
・人をつねる、叩く、蹴る、噛むなどの行動が多い
・爪かみ、歯ぎしりのくせがある
・声の音量調整が難しい
・ダンスやまねっこ遊びが苦手
なぜ現代の子どもは固有受容感覚が鈍くなりやすいのか?
1.デジタル機器の長時間使用
スマートフォン、タブレット、ゲーム機の普及により、
子どもたちが画面を見つめる時間が大幅に増加しています。
これらの機器を使用する際、
多くの子どもは前かがみの姿勢を長時間続けることになります。
同じ姿勢を長時間保持することで、筋肉や関節の動きが制限され、
固有受容感覚を司る受容器への刺激が減少してしまいます。
また、画面に集中することで、自分の体の位置や姿勢への意識が薄れ、
感覚の発達が阻害される可能性があります。
2.運動機会の減少
運動や外遊びは、様々な体勢や動きを通じて固有受容感覚を刺激し、
発達させる重要な機会です。
例えば、でこぼこした地面を歩くとき、
子どもの体は常にバランスを取ろうとして、
足裏や足首、膝の筋肉が微細に調整されます。
木登りやジャングルジムでは、
どの筋肉にどれだけ力を入れれば安全に移動できるかを体が学習します。
鬼ごっこやかけっこでは、
急に方向転換したり、スピードを調整したりすることで、
体の位置感覚や動きのコントロール能力が鍛えられます。
また、転んだり、ぶつかったりする経験も、
実は体がどこまで動けるか、どの程度の力が必要かを学ぶ
大切な機会です。
これらの多様な刺激がないと、
筋肉や関節にあるセンサーが十分に働かず、
「体の感覚」が育たないままになってしまいます。
その結果、自分の体がどんな状態にあるかを感じ取る力が弱くなり、
正しい姿勢を保つことが難しくなってしまうのです。
3.室内生活の増加
エアコンの普及により快適な室内環境が整う一方で、
子どもたちが自然環境で体を動かす機会が減少しています。
先にも書きましたが、
不安定な地面を歩く、木に登る、石を投げるなど、
自然の中での多様な動きは
固有受容感覚の発達に重要な役割を果たします。
平坦で安全な室内環境では、
バランス感覚や体の位置感覚を鍛える機会が限られてしまいます。
4.生活習慣の変化
早寝早起きの習慣の乱れ、
栄養バランスの偏り、
ストレスの増加なども、
神経系の発達に影響を与える可能性があります。
筋肉の収縮や神経の伝達に重要な役割を果たす
カルシウムやマグネシウムが不足すると、
体の位置を感じ取る力が弱くなりやすくなります。
また、睡眠不足は、神経系の発達や感覚統合に悪影響を及ぼし、
固有受容感覚の機能低下につながることがあります。
固有受容感覚の鈍さが子供の姿勢に与える具体的な影響
1.正しい姿勢を維持できない
固有受容感覚が鈍い子どもは、
自分の体がどのような位置にあるかを正確に把握することが困難です。
そのため、猫背や前かがみの姿勢になっていても、
それに気づかずに過ごしてしまいます。
また、正しい姿勢を意識的に取ったとしても、
その状態を維持するための筋肉の調節がうまくできず、
すぐに悪い姿勢に戻ってしまいます。
椅子に座る際の適切な深さや背もたれの使い方、
机との距離なども感覚的に判断できないため、
学習時の姿勢が悪化しやすくなります。
2.筋力のアンバランス
固有受容感覚の低下により、
姿勢を維持するための筋肉が適切に働かなくなります。
特に、体幹を支える深層筋(インナーマッスル)の活動が低下し、
表層の大きな筋肉に頼った姿勢維持を行うようになります。
この結果、一部の筋肉が過度に緊張し、
他の筋肉が弱化するという筋力のアンバランスが生じます。
首や肩の筋肉が常に緊張した状態となり、
頭痛や肩こりの原因にもなります。
3.バランス能力の低下
固有受容感覚が鈍いと、立位や歩行時のバランス能力が低下します。
片足立ちが苦手、転びやすい、階段の昇降が不安定などの症状が
現れることがあります。
これらの症状を補おうとして、
より安定した(しかし不適切な)姿勢を取ろうとするため、
さらに姿勢が悪化する悪循環に陥ります。
4.集中力への影響
不安定な姿勢を維持するために無意識に力を使うため、
学習に集中するエネルギーが分散されてしまいます。
実は、人間の脳は同時に複数のことを処理していますが、
使えるエネルギーには限りがあります。
固有受容感覚が鈍い子供は、正しい姿勢を保つことが自動的にできないため、
常に「今どんな姿勢かな」「倒れないようにしなきゃ」と
脳が姿勢維持に気を配り続けることになります。
椅子に座っている時も、
実は無意識のうちに首や肩、背中の筋肉に余計な力を入れて、
不安定な体を支えようとしているのです。
この「姿勢を保つための脳の作業」が常に背景で動いているため、
本来学習や課題に使うべき集中力や認知機能が、
そちらに奪われてしまいます。
例えば、スマートフォンでたくさんのアプリを同時に開いていると
動作が遅くなるのと同じで、
脳も「姿勢維持」というアプリを常に起動させていると、
「学習」というアプリに十分な処理能力を割けなくなるのです。
また、不安定な姿勢を保つための筋肉の緊張は、
知らず知らずのうちに体を疲れさせ、長時間の学習を困難にします。
子供の固有受容感覚を改善する方法
毎日の生活の中で、
固有受容感覚を刺激する活動を取り入れることが重要です。
・階段の昇降時に手すりを使わずに歩く
・片足立ちでの着替え
・目を閉じてのバランス遊び
など、簡単にできる活動から始めましょう。
家事のお手伝いも効果的で、
・掃除機をかける
・重い物を運ぶ
・料理や配膳の準備(野菜をちぎる、出来上がった料理を運ぶなど)
などは、バランスを取りながら様々な筋肉と関節を使うため、
固有受容感覚の発達に役立ちます。
また、 デスクや椅子の高さを子供の体格に合わせて調整し、
足裏全体が床につく環境を整えることもお勧めです。
家庭でできる固有受容感覚を鍛えるエクササイズ
1.バランス系エクササイズ
片足立ち:
最初は10秒から始め、慣れてきたら目を閉じて行います
つま先立ち歩き:
かかとを上げて爪先だけで歩く練習をします
一本橋歩き:
テープなどで作った直線の上を歩きます
2.筋力強化エクササイズ
動物歩き:
クマ歩き、カエル跳び、アヒル歩きなど、四つ這いでの移動を行います
壁押し:
壁に手をついて腕立て伏せのような動作を行います
重い物運び:
適度な重さの荷物を持って歩きます
ジャンプ遊び:
高い所から飛び降ります(怪我と、お住まいによっては騒音にはご配慮下さい)
相撲:
手押し相撲やお尻相撲、指相撲
3.感覚刺激エクササイズ
目隠し遊び:
目を閉じて物の形や位置を当てるゲームをします
粘土遊び:
手指を使った細かい作業で触覚と固有受容感覚を刺激します
マッサージ:
親子でお互いの背中や手足をマッサージし合います
4.力加減調節エクササイズ
・紙コップタワー作り
・ドミノ並べ
・積み木遊び
いずれも、積み上げたり、等間隔に並べたりと、
「そーっと置く」動きが良いエクササイズになります
整体での子供の姿勢改善アプローチ
固有受容感覚の発達と密接に関わる問題でもあり、
成長過程の今、改善に取り組むことで、
将来の健康への貯金になります。家庭での日常的なケア、適切な運動習慣、
必要に応じた専門的なサポートを組み合わせることで、
お子さんの姿勢改善と健やかな成長を促せます。
お子さんの将来の健康のために、今できることから始めてみましょう。
整体というジャンルにおいては、
当院では以下のようなことがお手伝いできます。
姿勢などの気になる点は、姿勢や動きを改善できるきっかけでもあります。
前向きに取り組むお手伝いができるよう、
日々子ども整体施術を行っています。
1.短時間で負担のかからない、手技による調整
子どもの体は大人と比べて柔軟性があるため、
短時間で、強い力は使わず優しい手技で調整を行います。
骨盤のバランスや関節の動きを改善し、
筋肉の緊張を和らげて調整を行うことで、
意識せず、自然な姿勢を取りやすい状態を作ります。
特に、肩甲骨と股関節を調整することで、
全体的な姿勢の向上が期待できます。
2.個別的な運動指導
お子さんの年齢や体力レベル、
保護者の方のご要望に応じた、
個別的な運動プログラムをご案内しています。
遊び要素を取り入れた楽しいエクササイズにより、
継続的な取り組みを促します。
保護者の方にも指導内容をお伝えし、
家庭でのサポート体制を整えます。
3.生活指導とアドバイス
日常生活や、習い事の内容、食生活など、
様々な角度からお話をお伺いしながら、
学習環境の改善、適切な道具の選び方、日常生活での注意点などを
アドバイスしています。
成長段階に応じた姿勢の変化についても説明し、
長期的な視点でのサポートを行います。